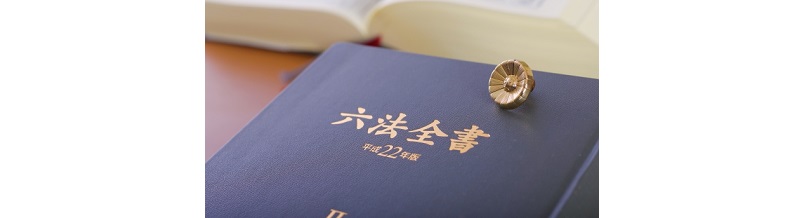相手が離婚届を提出しようとしていると知ったとき、多くの方は「なんとか話し合いで思いとどまらせよう」と考えます。
もちろん感情的な話し合いも大事ですが、法律的な準備と行動を同時に進めないと、感情では止められない場合が多いのです。
まずは法的な視点から「離婚届を止める権利」と「できる手続き」を知ることが第一歩となります。
【離婚届を出されそうなとき、法的に知っておくべき5つのポイント】
①「勝手に出された離婚届」は受理される可能性が高い
②離婚届の「不受理申出」を出せば事前に防げる
③偽造や詐欺的な離婚届の場合は刑事事件になる
④「協議離婚」は相手の一存では成立しない
⑤離婚調停・裁判になる可能性も見据える
【今すぐできる行動】
- 離婚届不受理申出を提出(役所で即日対応可能)
- 本籍地と住所地の役所に確認(どちらでも申出可能)
- 離婚届が提出された形跡がないか役所で確認
- 状況に応じて弁護士に相談
目次
「勝手に出された離婚届」は受理される可能性が高い
日本の協議離婚制度は世界的に見ても非常にシンプルで、夫婦双方が署名・押印した離婚届を役所に出せば、裁判所を通さずに離婚が成立します。
この手軽さが夫婦にとって良い面もありますが、片方が勝手に出してしまうリスクを高めている原因でもあります。
【なぜ「勝手に出された離婚届」が受理されやすいのか】
① 役所は「内容」を審査しない
役所(市区町村役場)は、離婚届を受け取った際に
・夫婦双方の署名・押印があるか
・必要事項がすべて記入されているか
この「形式要件」だけをチェックします。
内容の真偽や双方の本当の同意までは確認しません。
例えば:
- 配偶者が勝手に離婚届を用意し、無断で相手の署名を真似て記入した
- 昔渡した離婚届を無断で今提出した
→ 形式が整っていれば、原則受理されます。
② 本人確認が求められない場合が多い
離婚届の提出時に必ずしも本人確認や同席は必要ありません。
そのため、夫婦のどちらか一方だけ、あるいは代理人が提出することも可能です。
例:
夫が妻に内緒で離婚届を提出→役所は本人確認せず受理。
後で妻が気づいても、「既に受理済み」となるケースが実際にあります。
③ 不正を証明するのは困難
後から
「私は同意していない!」
と主張しても、受理された後の訂正や取消は非常に困難です。
偽造や詐欺的な提出であれば刑事事件にできますが、
- 筆跡鑑定
- 押印の真偽確認
- 手続き上の違法性の立証
など時間も費用もかかり、離婚成立を覆すのは簡単ではありません。
【結論:勝手に出されるリスクは「かなり高い」】
夫婦間の信頼が崩れている状況では、片方が独断で離婚届を出すケースは実際に多いです。
そして、形式が整っていれば役所は受理するため、「同意していなかった」は原則通りにくいというのが現実です。
【防止策:不受理申出は必須】
このリスクを防ぐためには、「離婚届不受理申出」を役所に提出することが最善策です。
・あなたが提出すれば、相手がどんな離婚届を出しても受理されません。
・一度提出すれば撤回しない限り有効です。
・本籍地または住所地の役所で手続き可能です(即日可)。
離婚届の「不受理申出」を出せば事前に防げる
日本の離婚制度では、夫婦の一方が勝手に離婚届を出しても、形式が整っていれば役所は原則として受理してしまいます。
このため、「知らない間に離婚していた」というケースも実際に発生しています。このリスクを防ぐ唯一の公式手続きが、離婚届不受理申出です。
【離婚届不受理申出とは?】
不受理申出(ふじゅりもうしで)とは、相手が勝手に離婚届を提出しても、自分の同意がない限り役所がその届を受理しないようにする制度です。
簡単に言えば、「離婚届を受け付けないでください」と役所に事前に伝える手続きです。この制度を利用すれば、相手が無断で離婚届を出すことは実質的に不可能になります。
【不受理申出の特徴】
● 有効期限なし
一度提出すれば自分が撤回しない限りずっと有効。
(※婚姻解消や本籍変更があれば別途対応が必要)
● 本籍地または住所地の役所で手続き可能
どちらでも受け付けてもらえます。
(本籍地が遠方の場合、郵送手続きができる役所もあります)
● 本人が手続きに行く必要あり
代理人や郵送ではできない場合が多い(役所によって異なるので事前確認が推奨)。
● 必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印でOK。署名だけで済む場合も)
- 本籍地が不明な場合は戸籍謄本が必要なことも
● 無料でできる
手数料はかかりません。
【手続きの流れ】
1.本籍地または住所地の市区町村役場に行く
2.「離婚届不受理申出」を提出したいと窓口で伝える
3.申出書に必要事項を記入
4.本人確認書類を提示
5.その場で手続き完了(受理証明書をもらえる場合も)
※窓口での所要時間は10~20分ほど。
【どんな場合に特に必要?】
- 配偶者が一方的に離婚を進めようとしている
- 感情的な衝突が続き、勝手に離婚届を出しそうな雰囲気がある
- 既に署名・押印済みの離婚届が相手の手元にある
- DV(ドメスティックバイオレンス)の懸念がある
これらの状況では不受理申出は「必須」と言えます。
【注意点】
- 片方だけの申出でOK:あなたが手続きをすれば、相手の意志にかかわらず効力を発揮。
- 家庭裁判所を経ない限り離婚できなくなる:相手が強行に離婚を求める場合でも、調停や裁判を経なければ離婚できなくなります。
- 調停・裁判の準備も並行して検討:不受理申出は一時的な防衛手段。相手が本気で離婚を望んでいる場合、次の段階を想定することも大切。
偽造や詐欺的な離婚届の場合は刑事事件になる
配偶者があなたの同意なしに離婚届を出した場合でも、
- 自分で書いたが、相手が黙って提出した → 民事トラブルの範囲(争いの余地あり)
- 署名や押印を偽造した → 完全に刑事事件
後者の場合は、もはや夫婦げんかの範囲を超えた重大な犯罪行為です。謝れば済む問題ではなく、法的に罰せられる行為になります。
【該当する主な犯罪と法律条文】
① 私文書偽造・変造罪(刑法第159条)
内容:
他人の名前や印鑑を勝手に使って書類を作成した場合。
罰則:
3月以上5年以下の懲役
⇒離婚届に勝手に署名・押印された場合はこれに該当。
② 偽造私文書行使罪(刑法第161条)
内容:
偽造した文書を役所などに提出した場合。
罰則:
私文書偽造罪と同じく3月以上5年以下の懲役
⇒離婚届を偽造して実際に提出した時点でこの罪も成立。
③ 公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)
内容:
役所に虚偽の事実(偽造の離婚届)を記載させた場合。
罰則:
5年以下の懲役または50万円以下の罰金
⇒離婚届は「公文書」扱いなので、虚偽の内容が記載されればこの罪にも当たる。
【立証方法と流れ】
● 証拠の確保
- 離婚届の写し(役所で取得可能)
- 押印や署名の筆跡鑑定(専門機関で依頼)
- 当時のLINEやメールなど、同意していなかった証拠
● 警察への被害届提出 → 受理されれば捜査開始
刑事事件として立件された場合、加害者(配偶者)は刑事処罰の対象となります。
【注意点:刑事事件のデメリットとバランス】
- 夫婦関係の修復はほぼ不可能になる:刑事告訴をすると、実質的に関係修復は断念する覚悟が必要。
- 親権・財産分与などにも影響:相手側の信用が大きく損なわれる。
- 捜査や手続きに時間がかかる:被害届から立件まで数ヶ月かかる場合が多い。
→刑事手続きに進む前に、感情面・家庭面・将来面を総合的に検討する必要があります。
「協議離婚」は相手の一存では成立しない
離婚は、法律上「夫婦間の契約解消」と見なされます。契約には双方の合意が必要です。
つまり、夫婦のどちらか一方の希望だけでは、離婚は成立しないというのが日本の法律の大原則です。
【協議離婚とは?】
日本で行われている離婚の約9割以上は協議離婚。これは、
- 夫婦双方が離婚に合意し
- 離婚届に署名・押印して
- 市区町村役場に提出する
この3つの条件が揃って初めて成立します。
⇒一方が「嫌だ」と言えば、離婚届が出されても無効と考えられます。
【相手の「一存」で成立しない理由】
① 合意は法律で義務づけられている
民法第763条(協議離婚):
「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」
⇒協議=話し合いと合意が必要という意味です。
② 署名・押印が必須
離婚届に夫婦双方の署名と押印がなければ受理されません。
(ただし、偽造された場合は刑事事件。先に説明したとおり)
③ 精神的な同意も必要
仮に署名があっても、相手が精神的に無理やり署名させられた場合や、意思能力が欠けていた場合には無効になる可能性があります。
【よくある誤解】
誤解①:「あなたが離婚に応じなくても離婚届を出せば成立する」
→ 間違い。不受理申出で防ぐことができ、合意しない限り正式には成立しません。
誤解②:「裁判をすれば絶対に離婚できる」
→ 間違い。裁判でも相手が法定離婚事由(不貞・暴力・悪意の遺棄・5年以上の別居など)を立証できなければ、裁判所は離婚を認めません。
【相手が無理やり離婚を進めようとしたら】
1.離婚届不受理申出を提出
2.相手に「私は合意していません」と明確に伝える(メールやLINEなど記録が残る形)
3.一方的な離婚手続きには応じない
4.弁護士に相談し、相手の行動を監視・記録
⇒これだけで、相手は「一存での離婚は不可能」と理解するはずです。
離婚調停・裁判になる可能性も見据える
相手が離婚届を提出できず、協議(話し合い)でも合意に至らなかった場合、次に進むのが家庭裁判所での離婚調停や裁判です。
ここで大切なのは、相手が本気で離婚を望んでいる場合は調停・裁判に進む可能性が非常に高いという現実を受け止め、準備しておくことです。
【離婚調停と裁判の違いと流れ】
① 離婚調停(家庭裁判所)
目的: 裁判所の調停委員(第三者)が間に入り、話し合いによる解決を促す。
特徴:
- お互い直接会わずに済む(別室対応も可)
- 合意すれば調停離婚が成立
- 合意できなければ不成立となり、次は裁判へ
注意: 裁判を起こす前に調停を経るのが法律上の原則(調停前置主義)。
② 離婚裁判
目的: 調停が不成立の場合、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判官が離婚するかどうかを決める。
特徴:
- 法律上の離婚理由(法定離婚事由)が必要
- 一方が反対していても裁判所が離婚を認める場合がある
【相手が裁判で主張できる「離婚理由(法定離婚事由)」】
民法770条で定められている主な理由は以下の5つ
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出るなど)
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由(DV、長期間の別居、極端な性格不一致など)
→相手がこれらを立証できなければ、裁判でも離婚は認められない。
【離婚調停・裁判に備えて今からすべき準備】
1.不受理申出で時間を確保
→ 勝手な離婚届提出をブロックし、冷静に準備する時間を確保。
2.相手とのやり取りを記録
→ LINE、メール、会話のメモ、録音などを残す(暴力・無責任行動などがあれば特に重要)。
3.離婚理由が成立しない証拠を集める
→ 浮気や悪意の遺棄など、相手の主張を否定できる証拠を用意。
4.弁護士に早期相談
→ 調停・裁判は法律の専門知識が不可欠。初期の相談が後々の結果を大きく左右します。
5.精神的な準備
→ 調停・裁判は時間がかかり、精神的な負担も大きい。カウンセラーなど第三者の支援も検討。